|
粉砕製法による分類で「乾式製法(乾式成形タイル)」と「湿式製法(湿式成形タイル)」の2種類に大別できます。乾式(かんしき)と湿式(しっしき)の違いは、大まかに水を使わない、湿式は水を使うの違いですが、成形の仕方はまるで違います。
乾式製法(乾式成形タイル)は粉状の原料を高圧のプレス機で成形したものです。湿式製法(湿式成形タイル)は土練機で原料を混練し、押出成形したものです。
この二つの製法は下図の色塗り線でその工程が示されているとおりです。製法が異なってできた製品の違いとして、一般的に湿式製法品はなめらかですが、乾式製法品はザラザラしています。この特徴がタイルの用途によって、使い分けられています。
基本的な製法についてはメーカー間の差はありませんが、工場設備などの違いにより、メーカー同士多少異なる部分があります。
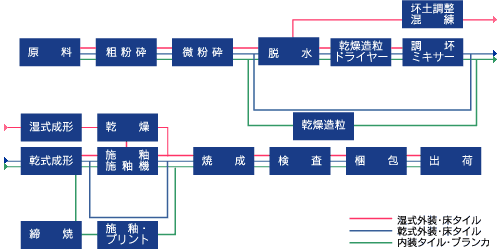
製造工程の図の出典:ダントータイルホームページによりました。
なお2016年現在では同ホームページから削除されています。
タイルを作る前の工程で必要な材料は「原料」と「顔料」の二種類です。下記にその製造工程を示しました。この二つは出荷後タイル工場に運ばれタイルが作られていきます
| ■ | タイルの原料の製造 | | ↓ | 原石採掘 | タイルの原料となる原石の採掘です。採掘するのは長石、陶石、粘土など。 | | ↓ | 調合 | 程度の揃えた原石をミル内に調合投入 | | ↓ | 湿式粉砕 | ミル内で粉砕し水を加えて、泥(どろ)状になるまで粉砕 | | ↓ | 泥調整 | ドロタンクに原料を移し、色調整等を施す | | ↓ | 造粒 | 調整されたドロ状の原料をスプレードライヤーで熱風、乾燥し、顆粒状に造粒する。顆粒のものを固めて粒の大きいものも作られる | | ↓ | 出荷 | 袋詰めして出荷 |
| ■ | タイルの顔料の製造 | | ↓ | 原石採掘 | タイルの顔料料となる鉱石の採取。コバルト化合物、銅化合物、マンガン化合物、クロム化合物、パナジウム化合物など。化合物とは、二種類以上の原料が化学合成によってできた物質のこと。 | | ↓ | 調合 | 指定された調合でミルに顔 料を 入れる | | ↓ | 湿式粉砕 | ミルにおいて適度な粒度になるまで粉砕する | | ↓ | 焼成 | 安定した顔料にする為焼成する | | ↓ | 湿式粉砕 | 用途に応じて再度ミルに入れて湿式粉砕をする | | ↓ | 乾燥 | スプレードライヤーにて乾燥 | | ↓ | 微粉粉砕 | 乾式着色用に更に細かく乾式粉砕する | | ↓ | 出荷 | 袋詰めして出荷 |
次にタイルの製造から出荷までの工程を示します。これがページの最初に示したタイルの製造工程になります。ここでは、解りやすいように簡略して説明します。
| ■ | タイルの製造 | | ↓ | 原料搬入 | 原料メーカーより原料調達 | | ↓ | 調合 | 決定された色合い、風合いを出す為に調合しミキサーで攪拌する | | ↓ | プレス準備 | 調合された原料をプレス成型機にセット | | ↓ | プレス成型 | 原料を押し固めて形を作る | | ↓ | 焼成 | 台車に積んでトンネル窯で焼成。温度は1250℃(酸化焼成) | | ↓ | 選別・梱包 | 良品のみ選別して箱に詰める | | ↓ | 出荷 | 各地へ出荷 |
タイルの原料となるものは、基本的に古来から変わりませんが、現在では次のようなものを使用しています。
 |  |  | | 長石(ちょうせき) | 陶石(とうせき) | 粘土(ねんど) |
地殻を構成する最も重要な造岩鉱物。ルミノケイ酸塩鉱物。造岩鉱物としてたいていの岩石に含まれ、ガラス光沢があり、ほぼ白色。
|
陶磁器の原料になる岩石の総称。一般に石英 (70%) と絹雲母 (30%) から成る。
|
岩石が風化や熱水作用によって分解してできた微細な粒子の集まり。地質学では粒径256分の1ミリ以下、土壌学では0.002ミリ以下をいう。
|
図出典:長石と粘土は丸美陶料㈱、陶石はエトーインダストリーによりました。
|
|